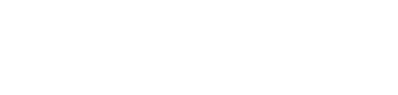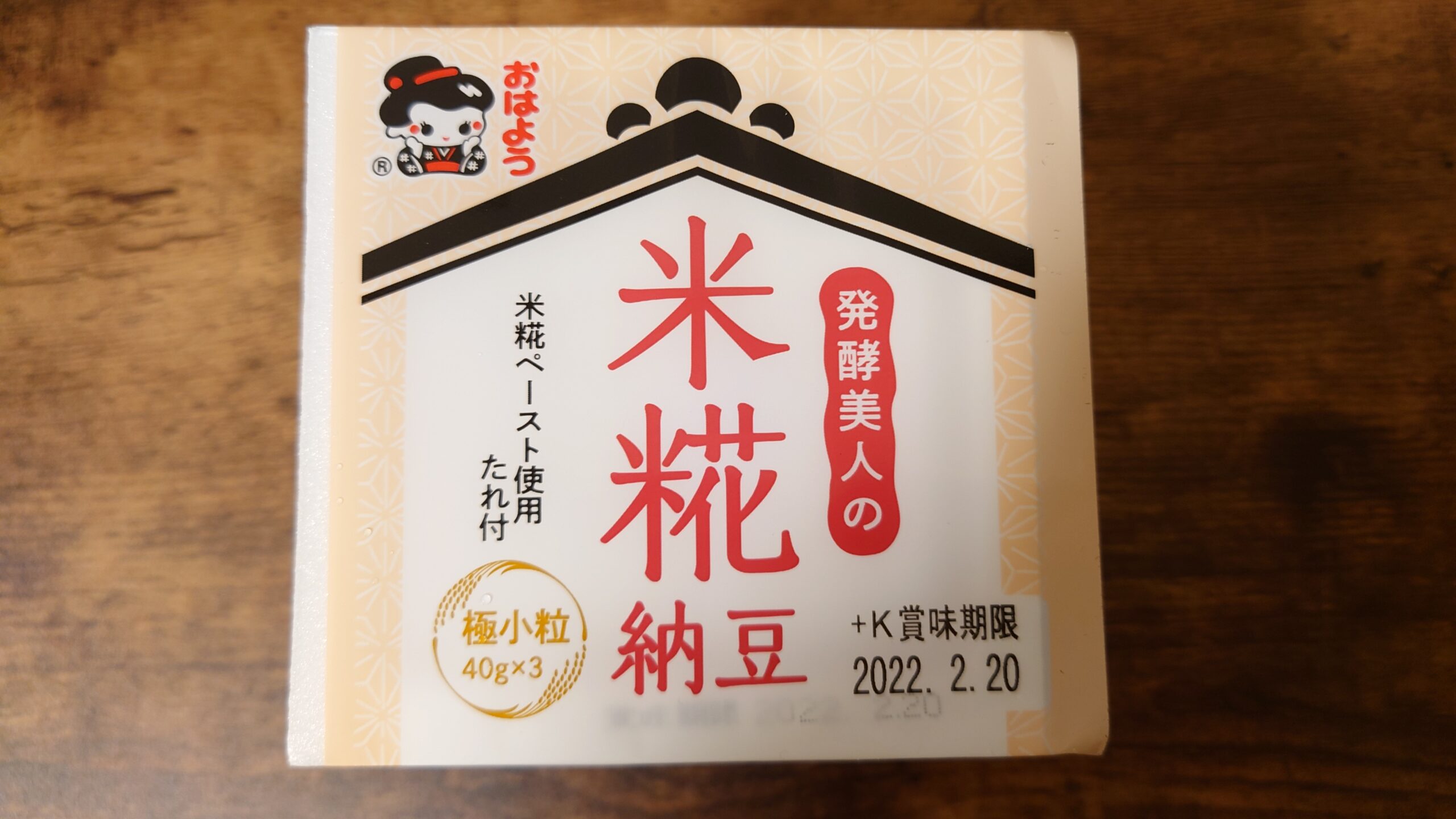オールドレンズの味わいが楽しめる現代レンズ「Voigtlander NOKTON classic 35mm f1.4 II SC」
オールドレンズのあの独特の写りに魅了され、オールドレンズ沼にはまる方も年々増えてきていると思います。
私もその一人で、様々なオールドレンズを買って使ってはそれぞれの強すぎる個性に振り回されて楽しんでいます。
ただ、今回ご紹介したいのはオールドレンズではなく現代レンズです。
今回は現代レンズなのにオールドレンズのような写りをするマニュアルフォーカスという尖ったレンズ「Voigtlander NOKTON classic 35mm f1.4 II SC」をご紹介します。

Voigtlander NOKTON classic 35mm f1.4 II SC
「NOKTON classic 35mm f1.4 II SC」は日本の光学機器メーカーのコシナから発売されているマニュアルレンズです。
Voigtlander(フォクトレンダー)というブランド名ですが、これはもともと1756年にオーストリアのウィーンで創業した光学機器メーカーの名前です。
そして現在ではコシナが商標権の通常使用権を持っているために、コシナの一部のレンズにVoigtlanderの名前がついています。
主なスペックは以下の通りです。
- 焦点距離: 35mm
- 口径比: 1 : 1.4
- 最小絞り: F16
- レンズ構成: 6群8枚
- 画角: 63°
- 絞り羽根枚数: 10枚
- 最短撮影距離: 0.7m
- 最大径×全長: Φ55.0×28.5mm
- 重量: 189g
- フィルターサイズ: Φ43mm
- マウント: VMマウント(ライカMマウント)
このレンズの最大の特徴はマニュアルフォーカスしか使えないマニュアルレンズというところです。
現代レンズではLeicaのレンズを除いてはかなり珍しいですよね。
マニュアルのみのおかげでレンズのサイズはかなりコンパクトです。
マウントはVMマウントとなっていますがライカMマウントと同じなので、マウントアダプターを使用する場合はMマウント用のものを用意すればOKです。
最短撮影距離が0.7mと最近のレンズとしては長めですが、これはもともとレンジファインダーのレンズであるライカMマウントのレンズではよくある仕様です。
外観・装着感
NOKTON classicは外観がクラシックでかなりかっこいいです。

正面には他のレンズと同様にレンズ名やブランド名が印字されています。
レンズコーティングの種類を示す「SC」には色がついていて、ひと目でわかるようになっています。
MCの場合は印字がないようです。

レンズ横には絞りの数字と焦点距離の印字があります。
これも特に焦点距離のメモリはマニュアルレンズならではですが、目で被写体との大体の距離を把握して、レンズのメモリを見て焦点を合わせるという使い方もできます。
開放では厳しいですが、ある程度絞っておけばスナップなどで使える方法です。

絞り羽根は10枚です。絞りを変更するときのカリカリというクリック感が心地よいです。

フジフィルムのX-T4に取り付けるとこんな感じです。
銀色の先端がかっこいいですよね。Leicaのボディに取り付けても絵になりそうです。

上から見るとこんな感じです。
マウントアダプターを付けてもかなりコンパクトですね。
また焦点距離の印字がかなりかっこいいです。
フジフィルムのXマウントに関しては最近「NOKTON 35mm F1.2」というレンズが出たのですが、個人的には見た目は「NOKTON classic 35mm f1.4 II SC」の方がかっこよくて好きですね。
レンズコーティングが選べる
NOKTON classic 35mm f1.4はレンズのコーティングがマルチコーティング(MC)とシングルコーティング(SC)から選ぶことができます。
マルチコーティングは現代のレンズと同じように何層にもコーティングが施されており、現代風のきれいな色味を楽しむことができます。
また逆光にもある程度耐性があります。
シングルコーティングはあえてコーティングを最低限にすることで、オールドレンズのような雰囲気の色味を再現しています。
こちらはフレアやゴーストへの耐性がかなり弱く、こういうところもオールドレンズっぽいです。
ちなみに個人的にはNOKTON classicを使うのであれば断然シングルコーティングがおすすめです。
というのもマルチコーティングでは良く写りすぎてしまうため、「マニュアルしか使えないコンパクトな現代レンズ」になってしまってNOKTON classicを使う意味合いが薄くなってしまう気がするためです。
Leica Summilux 35mm f1.4を意識した設計
コシナの公式HPなどでの謳い文句として「伝統的な対称形のレンズ構成」と書かれていますが、LeicaのSummilux 35mm f1.4(ズミルックス)をかなり意識した作りになっています。

写りは実際に比較すると違いは色々ありますが、クセの傾向は似ているとは思います。
(Summiluxの方がさらにクセが強いです)
Summilux 35mm f1.4の1stや2ndの新品はもちろんありませんし、中古市場も20万円以上するのでSummiluxが気になっているけどなかなか手が出ないという方にもおすすめです。
フォーカスリングの操作感が良い
NOKTON classicはマニュアルフォーカスのみのレンズなので、フォーカスリングを回して自分で焦点を合わせなければいけません。
そのためほぼ毎回フォーカスリングを操作するのですが、これがかなり良く作られています。
ちょうど良いトルク感でヌルっと回るというのでしょうか、とにかく回していて心地よいです。
ここは日本メーカーの品質の良さというのが出ていると思います。
フレア・ゴーストが強烈に出る
「SC(シングルコーティング)」の場合はフレアやゴーストが強烈に出るのもこのレンズも魅力です。
太陽光などの強い光を当てるとフレアやゴーストが発生するのですが、当てる角度によって出方が変わってきます。

光に対してレンズを直接向けると、このような砂時計のような形で光の輪ができます。

一方でレンズに対して斜め45°くらいの角度で光を当てると、このように細い虹のようになります。
個人的にはこちらの方が作品に生かしやすくて好きなのですが、この角度で太陽光を当てられるのは午前中の早い時間か夕方なので意外と時間が限られてしまいます。
光の当て方によるフレア・ゴーストの違いは研究のし甲斐があるので、好きな方はずっと遊んでいられると思います。
ブラックミストとの組み合わせもおすすめ
フィルターの「ブラックミスト」との組み合わせて使用することもおすすめです。
ブラックミストとは、ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑える効果があり、映画のような写りにできるソフトフィルターです。
通常のソフトフィルターと比べて白っぽくならないのも特徴です。

私のおすすめはKenkoのブラックミスト No.05です。
これは効果が強すぎず弱すぎずのちょうど良いバランスなので、つけっぱなしにしておいても良いと思います。
同じKenkoから「ブラックミスト No.1」という商品も出ているのですが、こちらは効果が強いので使う場面を選びます。
また他のメーカーからもブラックミストが出ていますが、Kenkoのブラックミストが一番手を出しやすい価格で良いと思います。

ブラックミストは49mmからしかないのですが、レンズの径は43mmなので取り付けにはステップアップリングを使う必要があります。

レンズに取り付けるとこんな感じになります。
個人的にはレンズ先端の銀色の部分がかっこいいと思っているので、そこが隠れちゃうのだけが少し残念です。。。

このように全体的に色味が淡くなるのと、玉ボケの部分がよりオールドレンズっぽい写りになります。
フレアも色がきれいに出てますね。
NOKTON classicとブラックミストの組み合わせは、より印象的な画が撮れるようになるのでおすすめです。
作例
それでは実際に私がこのレンズで撮った作例をご紹介します。

開放で撮った写真はピントが合っているところが浮き出るように立体感を感じます。
ボケも自然な感じできれいですよね。

完全マニュアルのレンズなのでスナップ撮影をするとピントが合っていないことも多々あるのですが、若干のピンとボケも作品にしてしまうような空気感が不思議です。
色味は全体的に落ち着いた色が出るので、アンニュイな表現が得意かもしれません。

開放で明るいところを撮影すると、軽くにじみが出ます。
ここもオールドレンズっぽくて味がありますね。
逆ににじませたくない場合はいくつか絞ってあげると改善します。

被写体がある程度遠くても、開放の状態でしっかりとピントが合います。
前ボケを活かした撮影もできますね。
まとめ
完全マニュアルフォーカスのレンズで操作にもかなり慣れが必要ですが、高性能な現代レンズとはまた違った作品を撮れる楽しいレンズです。
オールドレンズと違い状態の個体差もないので、オールドレンズが気になるけど中古で買うのに抵抗があるという方にもおすすめできます。
フィルムライクな表現の写真を撮りたい方はぜひ使ってみてくださいね。